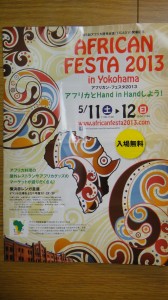先日、11歳のゴールデンレトリーバーが亡くなった。この子は以前睾丸の腫瘍ができて摘出手術をしたことがあり、病理組織検査でセミノーマとセルトリー細胞腫の2つが同時にみられる腫瘍でした。その数年後、定期的な健康診断で、副腎腫瘍が見つかり、左の副腎腫瘍の摘出手術をしました。病理結果はかなりめずらしい褐色細胞腫というものでした。その一年後の今回、ほんの少し足を挫いたようになった程度で、下腿骨の骨折をしてしまった。通常なら骨折の整復手術をして1~2ヶ月後にはまた走り回ることが出来たはずだったのですが、骨折部の遠位(下方)の骨端部に骨の吸収像と骨膜反応などが存在することが分かり、さらに肺のレントゲン写真で小さなマス(塊状)病変やリンパ節(前胸部・肺門部)の腫大が見られ、骨腫瘍または以前の腫瘍の転移と思われる所見が得られた。その結果今後の治療について飼い主の方とご相談をする事になった。
治療の選択肢の1つ目は通常の骨折の整復手術をした場合 : その予後は今回おそらく骨の腫瘍が原因で骨皮質がもろくなって骨折した可能性が高いので、術後もうまく修復しない可能性が高いのと、うまく整復できたとしても腫瘍の進行により、融解した骨腫瘍の部分で再度骨折する可能性が出てくる。
2つ目は骨折している右後肢の断脚手術をした場合 : 骨折部および腫瘍による疼痛はなくなり、3本足になっても反対側の関節疾患などがないので、通常の生活はできるようになる。しかし数ヵ月後には肺の腫瘍転移が次第に増大して肺癌で死亡することになるだろう。これは化学療法をしない場合、結局、断脚をしてもしなくても寿命に関しては変わらない。
3つ目は何もしなかった場合 : 骨折による疼痛と腫瘍による疼痛があり、腫瘍による疼痛はそれが進行してくるとさらに激しい疼痛を伴い、麻薬やそれにに相当する鎮痛剤を使用しても、なかなか痛みのコントロールが難しくなってくる。また肺の腫瘍はしだいに大きさや数の増加呼吸が苦しくなってきて、最終的には呼吸困難になってくる。
飼い主の方は以前よりあまり無理な延命処置を望まない方針でしたので、その他の化学療法や放射線療法、或いは四肢温存手術療法などは詳しく説明は致しませんでした。
これらをご説明してこれからのご希望をお聞きしましたら、大変悩まれ、いくつかのご質問にもお答えしましたが、しばらく結論が出ませんでした。そして最後に「もし先生のワンちゃんだったら、どうされますか?」という質問をされました。この質問は時々飼い主様から求められることがありますが、この回答は実は大変むずかしいことで、飼い主の方の治療に対する理解度、終末治療に対する考え方、その方の動物に対する思い入れ、個人の性格やその時の精神状態、家族の他の方との考えの相違、また、輸血治療など宗教に関与することもあり、色々なことに配慮してお答えしなければなりません。今回の飼い主の方は以前からよく存じ上げている方で、動物に対してあらゆる知識と経験をもっておられ、非常に冷静で客観的に物事を判断される方でしたので、私自身の考えを素直にお伝えしました。「私の子だったら、この段階ではとても決断するのは難しいですが、この先を考えると楽にしてあげる処置(安楽死)と言う選択をするかもしれません・・・。」 しばらく沈黙があり、次のような決断をされました。「この子が痛がったり、苦しんだりするのを見たくありません。ですから楽にしてあげてください。」目を赤くしてそう言った後、お別れをしたいので会わせて下さいとおっしゃって、ワンちゃんの顔を優しく撫でながら、何かを話しかけ、最後に一言やさしく「ありがとう、さようなら」といってお別れをしました。そして当院で一番古くから動物看護師をしている綿貫さんと抱き合って悲しみを共有しておりました。我々もこの飼い主の方の気持ちが充分わかるだけにスタッフも私も涙が溢れてしまいました。とても辛い決断でしたが、この子にこれ以上の苦痛を与えたくないという、とても深い愛情と思いやりの決断だったと思います。
こうした安楽死という辛い最後の決断は、人それぞれのお考えがありますので、必ずしも正当化されるものではないですし、もし自分がこの子の立場だったら、どう感じているかを考えてあげることも必要ではないかと思います。その上で飼い主がその子にとってベストな方法を選択されると良いのではないでしょうか。またわれわれ獣医療に携わる人間として、動物の体の状態や治療方法、治療後の予後(将来)等を伝えることはもちろん、さらに動物の”気持ち”を代弁してあげることも大切だと考えております。