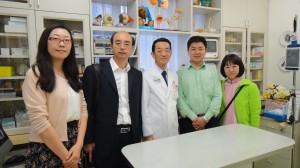ロータリクラブのインターシティーミーティングが3月2日鎌倉プリンスホテルで開催された。合同例会後の記念講演で自称”アマゾンの百姓”として農業を営み、アマゾニア森林保護植林協会会長でもある長坂氏の講演内容をご紹介しましょう。1990年に日本から集団の開拓移民がアマゾンの熱帯雨林の中に入って生活をする事になったが、当時の多くの移民のうち現在生き残っている人は長坂氏1人だけだそうで、その過酷な開拓するまでの様子を、笑いあり涙ありのとても感動的なお話をしていただきました。そしてご本人が開拓で体験した生活から3つのことが分かったそうです。
①アマゾンの熱帯雨林の中で生活するのに「1人では生きられない」ということ。:2年間全く1人で生活して、人と会うこともなく、言葉を喋らないでいると、人は頭が狂ってしまうというのです。奇跡的に出会った日本人医師が教えてくれた、いいかげんな食べ物、野草とココナッツの実、などで生きていたこともあったし、マラリアに罹り、毒蟻に刺された時の蟻酸がマラリアから救ってくれたこともある。
②そこで生活していると「人は食べるために生きるのか、生きるために食べるのか分からなくなってしまう。」ということ。
③大切なものは目に見えないものだということ。日光の温かさ、空気の味と香り。ブラジルの国土の65%が熱帯雨林であり、ここの森林が産生している酸素は地球上の空気の1/3にもなるそうです。
黄色人種とりわけ日本人は、皮膚の黄色と黒い瞳そして夏の暑さ、冬の寒さに耐えられる厳しい自然環境に耐えられる体質があるので、もっと自信を持って欲しい、さらにこれからの日本の若い人は度胸と実行力がある人間になって欲しいと付け加えた。
私達は食事や水に困らない生活をし、電気による生活で快適に過ごしているが、それが当たり前になってしまっており、長坂氏の経験した究極のサバイバル生活のお話をお聴きしたことで、自然の偉大さ・大切さに気付かされましたし、人は他人とのコミュニケーションによる社会生活がとても大切であることも再確認させられました。